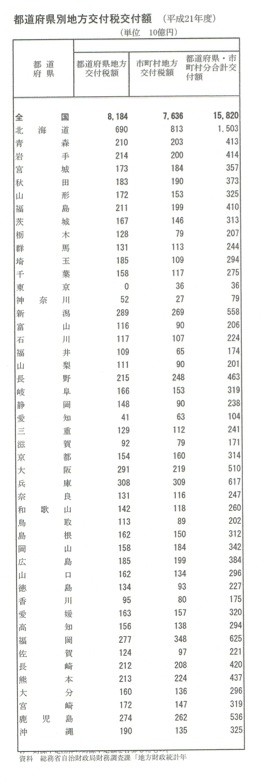現在、理化学研究所所属の研究員で早稲田大学で博士号を取得した小保方晴子を中心として発表したSTAP細胞ー刺激惹起性多能性獲得細胞問題が大きな議論を巻き起こしている。1月29日、小保方らは、イギリスの科学誌『Nature』に、STAP細胞についての論文掲載が決定したことを記者会見で発表した。再生医療などへの利用が見込まれる多能性獲得細胞としては、すでにiPS細胞ー人工多能性幹細胞があり、その開発者である山中伸弥京都大学教授はノーベル賞を受賞している。そのような期待とともに、中心的な研究者である小保方晴子がまだ若い30歳の女性であることとあいまって、発表当時は、大きな好意的反響をよんだ。
しかし、その後、他機関でのSTAP細胞再現実験が成功しない中で、小保方個人の研究者としての資質、さらに小保方らの研究成果自体への疑惑がインターネットなどで深まっていった。
大きくいえば、2つのことが指摘されている。まず、小保方晴子は2011年3月に早稲田大学で博士(工学)号を取得したが、その博士論文「三胚葉由来組織に共通した万能性体性幹細胞の探索」において、既存の文章を引用と明記せず、そのまま載せているということである。具体的にいえば、冒頭部分の約20ページ分の文章が、アメリカ国立衛生研究所のサイト「Stem Cell Basics」からの文章をそのままコピーアンドペーストしているとされ、参考文献紹介も他者のそれを使い回しているという。また、その中で使われている画像も別の企業が出したものをそのまま使っているのではないかという疑惑がもたれている。早稲田大学は、小保方晴子の博士号取得について検証をすすめる意向を示した。
他方で、今回の小保方などが発表した『Nature』掲載論文自体にも疑問符がつけられている。この論文の中でも、実験の手順を記した部分の一部が過去の研究のコピーアンドペーストであるのではないかと疑われている。また、実験の成果として出されている画像の一部が切り貼りなどで加工されており、さらには、別のテーマを扱っている博士論文の画像が使い回されていることも指摘されている。画像の加工については、小保方自身が「やってはいけないことという認識がなかった」と話しているそうである。そして、現在(3月27日)、共同研究者若山照彦山梨大学教授がSTAP細胞作成のためマウスの細胞を提供したが、そこから発生させたのではない細胞をSTAP細胞として提供した疑惑も浮上している。理化学研究所は論文の不備を認め、3月14日に小保方を含む論文執筆者全員に論文撤回をよびかけた。
この問題は、小保方晴子個人や、それに直接関わった研究者や教育研究機関(早稲田大学・理化学研究所・ハーバート大学など)固有の問題と考えられがちである。もちろん、直接に関わった個人や機関が直接の責任を負わなくてはならないのは当然である。そして、対処療法としては、個別の問題への対応が中心になるだろう。しかし、この問題について、個別の議論を離れてみてみると、現時点での日本の学術研究政策の失敗が、如実に現れていると思われる。
まず、研究者小保方晴子の養成について、近年の博士号取得者倍増政策の観点からみておこう。現在、ハーバード大学にて食事や遺伝子と病気に関する基礎研究に従事している医学博士の大西睦子は、3月17日、国際情報サイト「フォーサイト」において、STAP細胞問題について一通り紹介したうえで、次のように述べている。
■博士号を“乱発”してきた日本
そもそも、米国と日本では、博士号の品質が大きく異なります。2011年4月20日付 の『Nature』誌に、日本を始め中国、シンガポール、米国、ドイツ、インド、など世界各国の博士号の問題点が論じられています。
【The PhD factory,Nature,April.20.2011】
その中で、日本の博士号のシステムは危機に陥っていて、すべての国の中で、日本は間違いなく最悪の国のひとつだと書かれています。1990年代に、日本政府が、ポスドク(博士号を取得した後、常勤研究職になる前の研究者のポジション)の数を3倍の1万人に増やすという政策を設定しました。その目標を達成するために、博士課程の募集を強化したのです。なぜなら、日本の科学のレベルを一刻も早く 欧米と対等にしたかったからです。その政策で確かに 人数だけ は増えましたが、大学などのアカデミアでは、地位につける人数に制限がありますし、企業の就職には年齢の制限があるため、逆に、 ポスドクの最終的な職場がみつからないという状況に陥りました。さらに、博士号を取得する研究者 の質も低下しました。
日本の場合、ほとんどの学生が、修士号取得後のわずか 3、4年で博士号を取得して卒業します。いわば、博士号の“安売り”とも言える状況です。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140317-00010000-fsight-soci
このように、1990年代以降、日本は政策的に博士を3倍にする政策に乗り出したのである。しかし、博士の就職先は確保しなかった。博士課程在籍者は増えたのであるが、大学教員の増員など研究指導体制の強化ははかられなかったのである。そのため、一般的に、それぞれの博士課程在籍者への研究指導は弱体化し、博士号取得者の研究者としての質が低下することになった。他方、数としては増えた博士号取得者の就職難は、それ以前より競争によって激化することになったのである。
もちろん、この問題については、小保方個人やそれに関わった教育者、さらには、在籍した早稲田大学や留学先のハーバート大学の固有の問題も大きく影響しているだろう。また、理系と文系との違いもあるだろう。しかし、いくらなんでも、公開論文において、引用を明記せずに記載すれば、「盗用」の指摘は免れえない。そして、研究指導というものは、学部段階、修士段階、博士段階を通じて、そのような論文の作法を学んでいくものでもあるのだ。このことは、教育研究の失敗である。そして、その背景として、博士課程入学者を倍増したにもかかわらず、大学教員などの教育研究スタッフを増員しなかった政策自体を問題にしなくてはならないのである。
大学・研究機関における「競争主義」の高唱と学術研究体制の弱体化
他方で、幸運にも大学や研究機関に入ることができた研究者たちには、「成果」を競争しあうことが強制されている。鈴鹿医療科学大学学長であり、前国立大学財務・経営センター理事長、元三重大学学長であった豊田長康は、自身のブログの中で、主に国立大学を対象としながら、次のように述べている。
2004年から実施された国立大学法人化は、わが国における第二次世界大戦後の大学改革以来の大きな制度改革であるとされている。各大学には文部科学大臣が定めた中期目標を達成するための中期計画・年度計画の策定が求められ、その達成度が評価されることになった。予算面については中期目標期間(6年間)内については年度を超えた繰り越しが認められ、運営費交付金の学内配分が各大学の裁量で可能となった。また、ガバナンスの面では、学長と役員会の権限が強化されるとともに、経営協議会が設けられて外部委員が参画することとなり、監事制度も導入された。会計面では、民間の会計制度を参考にした国立大学法人会計制度が導入された。
ただし、運営費交付金については効率化係数がかけられ、総体としては年約1%程度の率で削減されることとなった。なお、法人化と交付金の削減は、制度上は必ずしも連動するものではないと説明されているが、現在までのところ国立大学法人の運営費交付金は削減され続けている。また、附属病院建設に伴う債務償還の補てんという意味合いを持つ“附属病院運営費交付金”については、法人化第1期において経営改善係数により急速に削減された。なお、法人化第2期には“附属病院運営費交付金”という区分は無くなった。
また、運営費交付金の種別については、主として職員の人件費や経常的な運営費等に使われる基盤的な運営費交付金が削減される一方で、国の定めるプロジェクトを競争的に獲得する運営費交付金が確保され、また、高等教育予算の中に国公私立大学が競争的に獲得する教育研究資金が確保された。
法人化によって、目標設定と評価によるマネジメント、競争原理の導入、ある程度の現場への裁量権の付与と民間的経営手法の導入、学長の権限強化と監視機構の導入等といった制度改革がなされ、それに伴い、各大学において様々な教学および経営面での改善・改革がなされ、今日に至っている。
法人化の大きな目的の一つは、国立大学の機能強化を図ることであると考えられるが、一方、経営の効率化も同時に求められている。基盤的な運営費交付金の削減は、この効率化に対応する政策であると考えられる。
しかし、運営費交付金の削減が、各大学の経営効率化の努力によってカバーできる範囲であれば大学の機能は低下しないが、その範囲を超えると機能が低下する。現在、少なくとも国立大学の研究機能については、運営費交付金の削減が、法人化によって期待される効率化を超えて“機能低下”を招いている状況であると推測される。
国立大学は、わが国の学術論文数の生産において大きな割合を占めているセグメントであり、その機能低下がわが国全体の学術論文数の停滞~低下を招き、その結果、世界の主要国が学術論文数を増やしている中で、わが国の研究面での国際競争力の急速な低下を招いているものと推測される。http://blog.goo.ne.jp/toyodang/e/2be2f339579a29b5f6bff219c24c45f5
豊田の主張は、国立大学法人化の中で、運営費交付金が減額されていくことで、学術研究体制が弱体化していっているということである。そして、その中で、競争的に獲得される教育研究資金が導入されていくことになるが、結局、そのように競争を強いても、学術研究体制の弱体化は免れないのである。結果として豊田は次のように指摘している。
また、主要15か国の比較では、日本以外の先進国が軒並み増加を示し、また、中国を初めとする新興国が急速に学術論文数を増加させているのとは対照的に、唯一日本だけが停滞~減少を示している。論文数については2001~04年にかけて、日本はアメリカ合衆国に次いで2番目の多さであったが、それ以後、イギリス、ドイツ、中国に追い抜かれ現在5番目となっている。
(中略)
これらのデータは、日本の学術論文数減少が、政治状況に大きな問題のある国以外には見られない、日本だけに起こった世界的に見て極めて特異な現象であることを示すものと考えられる。
(後略)
http://blog.goo.ne.jp/toyodang/e/3941ddc676f2625ee80c977d6740b448
以上より、日本は論文の数ばかりではなく、注目度(質)についても国際競争力が低下しており、特にイノベーションの潜在力を反映すると考えられる高注目度論文数(質×量)の国際順位が下がっていることは、今後の日本経済の国際競争力にも暗雲を投げかけるものと考える。
http://blog.goo.ne.jp/toyodang/e/f74e2e58c6531dc71ee8c19e772f4821
このような観点から、科学技術指標2013のデータにもとづき人口当りのTop10%補正論文数を計算し、その国際比較を示した。日本は科学技術指標2013にあげられている主要国の中では台湾、韓国に次いで21番目となっている。欧米諸国は日本の約2~10倍産生しており、台湾は日本の1.9倍、韓国は日本の1.4倍産生している。現在、日本の論文産生が停滞~減少していることから、この格差は今後さらに拡大すると想定される。
(中略)
このように、日本は先進国として、人口あるいはGDPに見合った論文数を産生しておらず、新興国と同じレベルになっている。今後、学術論文産生の停滞~減少状況が続けば、日本の順位はさらに低下し、イノベーションの「質×量」で他国を上回らなければ資源を購入できない国家としては、10~20年先の将来が危ぶまれる状況であると思われる。
http://blog.goo.ne.jp/toyodang/e/fd1b54eb1b8c903b2ff01b38a229ee77
数字や立論の検証については、上記ブログをみてほしい。豊田は、現時点において、日本の学術論文が数的にも停滞もしくは減少しており、注目度も下がっていると主張しているのである。「競争主義」が高唱される中で、日本の学術研究体制自体が、世界に比較して弱体化していることは、単に、国立大学だけでなく、日本全体に通底する問題であるといえよう。
このような競争主義は、独立行政法人である理化学研究所も同じである。例えば、毎日新聞は、次のような報道をしている。
特集ワイド:巨額研究費、理研が落ちた「わな」 予算の9割が税金 iPS細胞に対抗、再生医療ムラの覇権争い
毎日新聞 2014年03月19日 東京夕刊
「科学者の楽園」と呼ばれる理化学研究所(理研)は税金で運営される独立行政法人だ。新たな万能細胞「STAP細胞(刺激惹起(じゃっき)性多能性獲得細胞)」の研究不正疑惑が理研を激しく揺さぶっている。カネの使われ方から問題の背景を読み解く。【浦松丈二】
寺田寅彦、湯川秀樹、朝永振一郎……。日本を代表する科学者が在籍した理研は日本唯一の自然科学の総合研究所だ。全国に8主要拠点を持ち職員約3400人。2013年度の当初予算844億円は人口20万人程度の都市の財政規模に匹敵、その90%以上が税金で賄われている。
予算の3分の2を占めるのが、理研の裁量で比較的自由に使える「運営費交付金」。STAP細胞の研究拠点である神戸市の理研発生・再生科学総合研究センター(CDB)には年間30億円が配分される。研究不正の疑いがもたれている小保方(おぼかた)晴子・研究ユニットリーダーは5年契約で、給与とは別に総額1億円の研究予算が与えられている。
英科学誌「ネイチャー」に掲載されたSTAP細胞論文の共著者、笹井芳樹CDB副センター長は、疑惑が大きく報じられる前の毎日新聞のインタビューで「日本の独自性を示すには、才能を見抜く目利きと、若手が勝負できる自由度の高い研究環境が必要」と語り、この10年で半減されたものの運営費交付金がSTAP細胞研究に「役立った」としている。理研関係者によると、小保方さんに「自由度の高い」研究室を持たせ、大がかりな成果発表を主導したのは笹井さんだった。
「万能細胞を使った再生医療分野には巨額の政府予算が投下されている。そのカネを牛耳る“再生医療ムラ”内には激しい予算獲得競争、覇権争いがある」と指摘するのは近畿大学講師の榎木英介医師だ。学閥など医療界の裏を暴いた「医者ムラの真実」の著書がある。失われた人間の器官や組織を再生することでドナー不足や合併症などの解消が期待される再生医療分野に対し、政府は13年度から10年間で1100億円を支援することを決めている。
榎木さんは言う。「現在、政府予算の大半がiPS細胞(人工多能性幹細胞)の研究に回されています。顕微鏡1台が数百万円、マウス1匹でも数千円から特殊なものでは万単位になる。予算が獲得できなければ研究でも後れを取ってしまう。追いかける側の理研の発表では、山中伸弥京都大教授が生み出したiPS細胞に対するSTAP細胞の優位性が強調され、ピンク色に壁を塗った小保方さんのユニークな研究室内をメディアに公開するなど、主導権を取り戻そうとする理研の並々ならぬ意欲を感じた」
笹井さんはマウスのES細胞(胚性幹細胞)から網膜全体を作ることに成功した再生医療分野の著名な研究者。榎木さんは「山中教授がiPS細胞を開発するまでは、笹井氏が間違いなくスター研究者だった」と言う。だが、iPS細胞が実用化に近づいたことで、笹井さんら“非iPS系”研究者の間では「埋没してしまうのでは」との危機感が高まっていたといわれる。
「こうした競争意識が理研の“勇み足”を招いたのではないか」(榎木さん)
霞が関でも研究予算を巡ってのせめぎ合いが繰り広げられている。「民主党政権時代がそうだったが、本来の『国立研究所』は不必要だ、第1級(の研究レベル)でなくても2級3級でいいというのであればそれまでだ。しかし、必要だというなら現在の独立行政法人制度では全く不十分だ。手をこまねいていては欧米の一流研究所を超えることはなく、躍進する中国の国営研究所に一挙に追い抜かれるだろう」。昨年10月23日、中央合同庁舎4号館の会議室でノーベル化学賞受賞者の野依良治・理研理事長が熱弁をふるった。世界に肩を並べる研究開発法人創設についての有識者懇談会で意見を求められたのだ。トップレベルの研究者に高額の報酬を支払えるようにしたい、それには法律で給与などを細かく定められた独立行政法人の枠組みから出なければ−−との訴えだ。
実際、米ハーバード大学など一流大学の教授年収は約2000万円。世界トップレベルの研究者で5000万円を超えることは珍しくない。一方、理研の常勤研究者の平均年収は約940万円。これでは優秀な頭脳が海外に流出したとしても責められまい。
「科学者に科学者の管理ができるのか」。財務省関係者からはそう不安視する声が聞かれたが、理研関連の来年度予算編成が大詰めを迎えた1月末、理研はSTAP細胞論文を発表。政府は早速、理研を「特定国立研究開発法人」の指定候補にすることを発表し、野依理事長の訴えは実りかけた。ところが、論文に画像の使い回しや他論文からの無断転載が相次いで見つかり、政府は閣議決定するまでの間、理研の対応を見極める方針だ。指定の「追い風」として期待されたSTAP細胞は逆に足かせになってしまったのだ。
有識者懇談会委員の角南(すなみ)篤・政策研究大学院大学准教授は「チェック体制は制度改革の論点の一つで、そこがクリアできないなら理研の新法人指定は簡単ではない」と言う。「研究不正疑惑はいつでもどこでも起き得る問題だが、この時期に新制度の旗振り役である理研で起きてしまったことが、科学技術振興を成長戦略の柱と位置付ける政権の推進力に悪影響を及ぼさないことを願いたい」
(後略)
http://mainichi.jp/shimen/news/20140319dde012040002000c.html
まず、理化学研究所も、一般の国立大学同様、運営費交付金が減額されていることに注目しておきたい。理化学研究所のサイトに掲載されている年度計画の各年度予算によると、2005年度に運営費交付金が711億200万円であったが、それ以降次第に減額されて、2013年度は553億3000万円となっている。しかし、予算総額は2005年度が867億6900万円から2013年度には905億3900万円となっている。このように、一般的経費にあてられる運営費交付金が減額される中で、それまでの研究費を確保するためには、競争的資金を導入せざるをえなくなっているのである。そして、再生医療の分野において、理化学研究所側は、京都大学教授山中伸弥のiPS細胞開発に遅れをとっていた。そこで、注目されたのが、小保方晴子の提唱していたSTAP細胞だったといえるのだ。理化学研究所は、小保方晴子を採用し、多額の研究費を与えたのは、そのような意図であったと思われる。
しかし、結局のところ、小保方の研究においては、研究成果の「証拠」である画像そのものに疑惑がもたれることになった。これが意図的であるかどうかははっきりしない。そもそも「画像の加工」自体に「やっていけないことという認識がなかった」という小保方に、どれほどの責任意識があるのかとも思う。だが、小保方は、いうなれば理化学研究所の期待に応えようとしていたともいえるのだ。競争主義にさらされ、「成果」をあげることが一般的に強制されており、その中で、「成果」をデコレーションしようという誘惑にかられることは研究者個人としてあり得るだろう。短期間に「成果」をあげないと研究者自身が職を失うことになるのである。
他方で、「成果」をあげたとする研究について、競争状態に置かれている理化学研究所側も、短期に発表し、特許などの優先権を確保し、予算を獲得したいという意識がはたらき、研究をチェックしようという意識が減退していくことも容易に想像できる。少々問題があっても、追試に成功すればよいということになるのだ。これは、理化学研究所の問題であるが、競争を強いられている日本全体の大学・研究機関のどこでも起こりうることなのである。競争主義の高唱がもたらす日本の学術研究体制の弱体化の象徴といえるだろう。
安倍政権の新成長戦略に打撃を与えたSTAP細胞問題
さて、前述の毎日新聞の記事は、政府の新成長戦略の一環としての科学技術振興政策に、今回の問題が打撃を与える可能性を指摘している。より、直接的に産経新聞が下記のように報道している。
STAP論文 中間報告 出はなくじかれた新成長戦略
産経新聞 3月15日(土)7時55分配信
政府は、「STAP細胞」の論文を発表した小保方晴子・研究ユニットリーダーが所属する理化学研究所の改革を、安倍晋三政権が重視する6月の新成長戦略の一環と位置付けていた。だが、今回の事態を受けて、理研を軸に描いていた技術立国構想は出はなをくじかれる形となり、第3の矢の成長戦略にも影を落としそうだ。
政府の総合科学技術会議(議長・安倍首相)は12日、世界最高水準の研究を目指す新設の「特定国立研究開発法人」(仮称)の対象候補を、理研と産業技術総合研究所に決めた。だが、正式な決定は見送られた。政府関係者によると、論文の疑惑が浮上する前は、同日の会議で正式決定の運びだったという。
小保方氏がSTAP細胞の存在を発表すると、政府は世界的なニュースとして歓喜した。首相は1月31日の衆院予算委員会で「若き研究者の小保方さんが柔軟な発想で世界を驚かせる万能細胞を作り出した」と称賛。下村博文文部科学相は同日の記者会見で「将来的に革新的な再生医療の実現につながりうる」と述べ、理研をはじめ基礎研究分野への予算配分強化の方針を打ち出した。
14日、菅義偉(すが・よしひで)官房長官は記者会見で「理研は国民に一日も早く結果を示す必要がある」と述べるにとどめ、理研の対応を見守る方針だ。山本一太科学技術担当相は記者会見で「関心を払わずにはいられない。しっかり意見も言っていかなければいけない」と指摘した。
政府としては、新成長戦略の当てが外れることになりかねないばかりか、論文に故意の不正があったと判断されれば、組織体制をただすなど理研に厳しい対応を取らざるを得ない場面も想定される。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140315-00000093-san-soci
いうなれば、安倍政権は、新成長戦略の柱の一つに科学技術の振興をあげ、そのため、「特定国立研究開発法人」に理化学研究所を指定しようとしていた。つまりは、「競争主義」において「成果」を出したものたちを、これまで以上に優遇しようとしていたのである。しかし、その「成果」とは何だったのだろうか。STAP細胞問題は、安倍政権の新成長戦略の柱も揺るがすことになったのである。
だが、結局、それは必然的であったのだと思う。博士号取得者の倍増、競争的資金の導入、「成果」至上主義は、競争こそが進歩であるという新自由主義的な思い込みから出発したといえる。もちろん、ある程度、成果を出す競争にさらされるほうが効率的な研究分野もあるだろう。しかし、学術研究とは、単に「有効性」を早期に成果として出すだけのものではない。そもそも、文系・理系を問わず、学術研究とは、自らの主体を含めた「世界」とはどのようなものであり、どのような仕組みで成り立っているのかを問うでもあるのだ。そして、学術研究の「有効性」も、上記のような問いに支えられているのである。近視眼に「成果」を求めて競争させることを至上にした、近年の学術研究政策の失敗を象徴するものがSTAP細胞問題であったと考えられるのである。このように失敗した学術研究政策に立脚したのが、安倍政権の新成長戦略の一環としての科学技術振興であったといえよう。
追記:小保方晴子個人やSTAP細胞の概略については、Wikipediaの当該記事を参考とした。
Read Full Post »