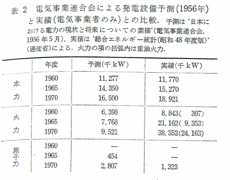-
1、原子力規制委員会記者会見からの「しんぶん赤旗」の排除
2012年9月26日、共産党の機関紙である「しんぶん赤旗」は、次のような記事をネット配信した。
原子力規制委員会が毎週1回開く委員会終了後の記者会見について、同委員会の実務を担当する原子力規制庁の広報担当者は「特定の主義主張を持つ機関の機関紙はご遠慮いただく」などとして、「しんぶん赤旗」を排除する方針を25日、明らかにしました。さらにフリーランスの記者についても「どういった雑誌に、どういった記事を書いているかを見て、特定の主義主張を持って書かれている方はご遠慮いただいています」と、憲法が禁止する検閲まがいの対応をしていることも明言しました。
原子力規制委員会の田中俊一委員長は19日の第1回委員会で、「地に落ちた原子力安全行政に対する信頼を回復する」ため「透明性を確保する」と述べ、「報道機関への発表を積極的に行うことで、委員会としてのメッセージを分かりやすく伝える」とする方針も決めていました。委員会で決めた「報道の体制について」では「報道機関を既存官庁よりも広く捉え、報道を事業として行う団体や個人を対象にする」とまで明記していました。
これまで、内閣府原子力安全委員会後の委員長らの記者会見で、こうした対応はされていませんでした。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2012-09-26/2012092614_03_1.html
つまり、「特定の主義主張を持つ機関の機関紙」として「しんぶん赤旗」所属記者を記者会見から排除するとともに、フリーランスの記者についても、「特定の主義主張を持つ」かどうかで選別すると、原子力規制委員会は明言したということである。
-
2、原子力規制委員会の初仕事としての原子力「言論」規制
翌26日、原子力規制委員長田中俊一の第一回定例記者会見が開かれた。その際、この問題が記者から質問された。一応、典拠として、この記者会見の映像をあげておこう。大体10分過ぎあたりから、この問題のやり取りが記録されている。
ブログ「みんな楽しくハッピーがいい」で、この部分のやり取りがおこされている。まず、フリーランスの記者から、次のような質問があり、原子力規制委員会の事務局である原子力規制庁の広聴広報課長が、このように答えている。
フリーランス:
フリーランスのWatariと申します。
本日の赤旗の記事で、今日のこの会見にですね、赤旗の記者の参加が認められないという事を、原子力委員会の広聴広報課の方からあったということだったんですけれども、その際にフリーランスの人間も含めて、報道内容を精査し、偏った主義主張の報道媒体、あるいは記者には記者会見の参加を認められないというふうに、委員会の方から連絡があったという事を記者から直接聞いたんですけれども、そのことが事実か?っていうことと、「開かれた報道」という事を前提として、この委員会でそういうことは委員長として、見解としてどうなのか?ということと、それから「偏った報道」というのは、たとえば、フリーランスには限らないと思うんですけれども、どこまでのことをいうのか?と。
朝日新聞、読売新聞、産経新聞、毎日新聞等々はですね、「毎日社説で偏った主張をされている」と僕は思っていますけれども、そうしたものは偏っていなくて、他の物は偏っているという基準を教えて下さい。(中略)
広聴広報課長:
わたくし広聴広報課長でございますので、まず事実関係から説明させていただきますと、フリーランスの方でそういう主義主張を確認するというような事はございません!
わたくしどもが申し上げているのは、先の19日の委員会決定でもございましたけれども、フリーランスの方の実績ですね。これまでの活動実績として、どういう記事が、掲載されてきたのか、それが出来るだけ最近に掲載されているのか。というような事を見させていただくという事はございますけれども、記事の内容を確認するという趣旨ではございません。
フリーランスの方のそうした活動の、顕著な方を優先して対象としたいという思いでございますので、特定の主義・主張で判断するという事ではございません。
というのが事実関係でございます。フリーランス:赤旗はどうなの?
広聴広報課長:
赤旗さんにつきましては、こちらは政党の機関紙という事でございまして、報道を事業とするという趣旨からいくと、少し違うんではないかという事で、いわゆるフリーランスの方っていうのは報道を事業とされる方かと思います。
そうした方々を優先的に、こうした記者会見の場でお招きして参加いただくということを申し上げたという事でございます。フリーランス:政党機関紙以外は・・(聞きとれない
広聴広報課長:少し繰り返しになりますけれども、フリーランスの方であればですね、
フリーランス:フリーに限らないで、直接の意味は、政党機関の…(聞き取れない
広聴広報課長:
政党の機関紙というよりは報道を事業としている方という事を、一つの基準として考えさせていただいています。はい。
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-2385.html
そして、広聴広報課長は、次のように「記者会見」の資格について述べたのである。
第一回の委員会の資料で、「報道の体制について」という中で、資料の16ページ17ページにありましたけれど、記者会見等に参加を求める報道機関の範囲は次の通りにするとか言って、いわゆる新聞協会、あるいは専門新聞協会、あるいはインターネット報道協会、等々の会員である方。あるいはこうしたものに準ずるような方というようなことで、一つの基準は示させていただいているところでございます。その中に、いわゆるその報道を事業と、最初の趣旨のところでですね、報道事業として行う団体や個人を対象にする。というふうに掲載させていただいています。
という、ことでございます。
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-2385.html
いわば、「報道事業者」に記者会見参加者を限定するとしたのである。その上で、政党機関紙である「しんぶん赤旗」は参加資格がないと述べている。ここであげている「報道の体制について」という文書において、いわゆる記者クラブ会員以外の記者会見参加者は「発行する媒体の目的、内容、実績等に照らし、上記いずれかに準ずると認め得る者」「上記メディアが発行する媒体に定期的に記事等を提供する者であって、その実績等を認め得る者」とし、その判定の基準を「発行媒体の目的・内容・実績の報告を求め、これらを証する資料の提出を求めて、準ずるか否かを判定する」などとしている。いわゆる「検閲」というのは、このことをさしていると思われる。なお、広聴広報課長は「内容」はみないとしているが、この文書では「内容」も判定基準としている。ということは、今後、具体的な運用がすすめば、「内容」も判断基準として記者会見参加者の選別が行われるのであろう。結局、原子力規制委員会の初仕事は、記者会見参加者の選別という形で行われる、原子力「言論」規制なのである。
-
3、原子力規制委員長田中俊一の本末転倒な「政治的中立」論
フリーランスの記者に続いて、「週刊金曜日」の記者が、「しんぶん赤旗」は報道事業として成立っており、報道事業者に該当するのではないかと質問した。それに対し、田中俊一は、次のように答えた。
これは答えにくいところですけれども、政治からの独立っていうのがこの委員会の非常に大きな、プリビレージ、それがありますので、政党っていうのは政治とダイレクトに政治の力を表に出す一つの手段として使われているのが、政党の機関紙じゃないかと思うんですね。
これは私の考えですけれども。
ですから、そういうところで、そういう方を同じにっていうふうにやってしまうと、政治からの独立っていうことが、少し怪しくなるかなっていう感じはしないことはないですね。
これはみなさんが、是非、皆さんで考えていただいた方がいいと思いますけれども、私はそんなふうに思うところがありますね。
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-2385.html
田中俊一が「しんぶん赤旗」を排除する理由は、原子力規制委員会が政治的に中立でなければならないからというのである。彼にとって、政党の機関紙である「しんぶん赤旗」に書かれることは「政治の力を表に出す一つの手段」なのである。
原子力規制委員会が、政治的中立を求められるのは、推進側との一体化をさけるためであった。6月15日の参議院本会議で、原子力規制委員会設置法案の共同提出者の一人である民主党の近藤昭一衆議院議員は、次のように述べている。
衆議院議員(近藤昭一君) 法案提出者の衆議院議員の近藤昭一でございます。
原子力規制委員会を三条委員会としたその理由について、お答えをさせていただきたいと思います。
これまでの原子力規制においては、原子力発電の推進を担う経済産業省とその規制を担う原子力安全・保安院とが一体となっていたため、独立した規制上の判断と決定が担保されず、安全規制がゆがめられる事態が生じておりました。
新たな規制組織をどのようなものとするかについて、政府案は環境省の外局として原子力規制庁を設置するものでありましたが、本法案では原子力規制組織を独立行政委員会、すなわち三条委員会として設置することとし、十分な権限、人事及び予算が担保された上で、原子力事業者のみならず、他の行政機関や政治部門からも独立して職権を行使することが可能な組織となっております。
そして、原子力規制委員長に田中俊一が不適格であるとして世論が反対するのは、彼が日本原子力研究開発機構という、原発の推進側にいた人物であるからということである。原子力規制委員会設置法は第7条の中で、「原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理若しくは廃棄の事業を行う者、原子炉を設置する者、外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせる者若しくは核原料物質若しくは核燃料物質の使用を行う者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)若しくはこれらの者の使用人その他の従業者」は原子力規制委員になれないと決めている。つまり、彼自体が委員長の職にいるということ自体が、原子力規制委員会の中立性を侵犯しているのである。つまり、彼が政治的中立を云々する時点で、本末転倒なのである。
その上で、彼は、「しんぶん赤旗」に書かれることを「政治的圧力」として把握している。しかし、「しんぶん赤旗」紙上で指摘されるということは、別に、他の新聞ー例えば朝日でも読売でもいいがーで書かれることと、手段において差はない。それは、政治的な圧力ではなく、公開の場の言論にすぎないのである。田中の発言は、政治的圧力と公開の場の言論による批判を混同したものなのである。確かに、「しんぶん赤旗」記者の質問は批判的なものであろう。しかし、その批判的な質問により、原子力規制委員会の問題点がよりあきらかになる。そして、当たり前のことだが、「しんぶん赤旗」記者の行った質問によってあかされたことは、単に「しんぶん赤旗」の読者だけでなく、他の新聞の読者にも共有される可能性を有する。その意味で、公開の場での言論による批判は、社会の共有財なのであるといえる。
特に、原子力規制委員会設置法では「原子力規制委員会は、国民の知る権利の保障に資するため、その保有する情報の公開を徹底することにより、その運営の透明性を確保しなければならない。」(第25条)と、情報公開を徹底することを規定している。これは、福島第一原発事故で情報が隠蔽されたことの反省に基づいたものである。その意味で、田中らの発言は、そもそも原子力規制委員会設置法にも反するとともに、福島第一原発事故から何も学んでいないことを自ら暴露したものであるといえる。
このブログで、田中俊一の放射線規制に対する考え方は規制委員長として不適格ではないかと指摘したことがある。しかし、そもそも、「政治的中立」という「公人」としての第一原則まで理解できない人物とは思わなかった。しかし、考えてみれば、原子力規制委員会設置法自体が、彼のような存在を原子力規制委員としては不適格としているのであり、そのことに思い当たらないがゆえに、原子力規制委員長の職につくことになったのだろうと思う。つまり、前述したように、政治的中立を侵犯している人物自体が、記者会見参加者の「政治的中立」を云々するという、逆さまなことになっているのである。
このままいれば、より晩節を汚すだけだと思う。国会の同意不同意にかかわらず、本人のためにも一刻も早く辞任すべきであると思う。いずれにせよ、原子力規制委員会は原子力「言論」規制委員会になりはてているのだ。